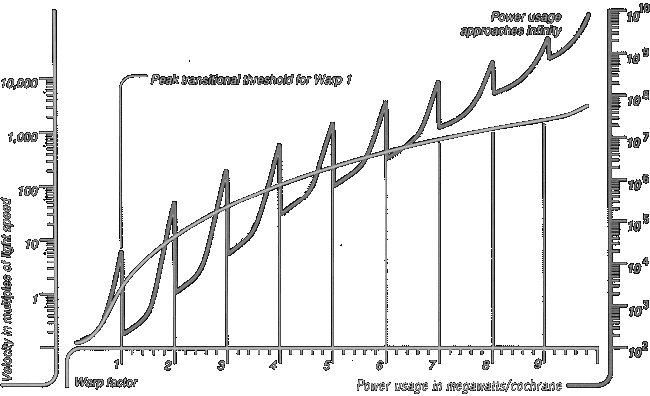ワープエンジン
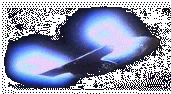
 Warp!
Warp!
 Warning! Damaged to warp core...
Warning! Damaged to warp core...
ワープエンジンは西暦2061年、Zefram Cochrane (2030-2117)によって発明された。この時、彼と彼の研究チームは、核融合反応炉から発生するプラズマを亜空間コイル(subspace distortion generator coil; 後にワープコイルと呼ばれる)に流し込む事により、無人実験機の光速での飛行を成功させたのである。世界大戦で世界が疲弊していた2063年4月4日、Cochrane博士らは核ミサイルを改造して建造した初の有人超光速船『フェニックス号』に乗り込み、見事ワープに成功した。この時、偶然にも太陽系を探索に来ていたバルカン船と遭遇して幸運にもバルカンとのファーストコンタクトを果たした。
ワープエンジンは、持続的に空間を折り曲げて推進 (continuum distortion propulsion)する。その間、エンジンはワープを維持するために常に時空を曲げておかねばならない。ただ放置しているだけでは速度が維持できないのである。ワープ航法では、ワープエンジンに常にエネルギーを注入しないと亜空間フィールドが崩れ、船はワープ状態から離脱してしまう。ニュートン力学的な慣性で航行することは出来ないのである。
ワープエンジンは、強力なワープフィールド(亜空間フィールド)を形成して宇宙船を包む。亜空間フィールドは何層も重なって形成され、それぞれが相対的に運動して超光速を出す。ワープエンジンが作る亜空間フィールドは、亜空間殻(ワープシェル)とでも呼ばれるように、場のエネルギーは船外の特定の位置で最大となる。船そのものは通常空間に浮かんでいる。
ワープエンジンは通常左右2基あるので、ワープフィールドは2つのシャボン玉がくっついた形になる。しかし中にはピカード艦長が以前指揮していた USS Stargazerのように、エンジンが4基あるものもある。特殊な例としては3基の船もあるが、飛行安定性はあまり良くないらしく、普通は見られない (例:"All Good Things..."[TNG] のEnterprise-D)。
左右にエンジンがあるとはいえ、たとえば微妙に左右の出力を調整してカーブしながらワープ航行する、ということはできない。あくまでワープの基本は直線航行であり、方角を変える必要がある場合は、いったんワープを解除して通常空間に出たあと、スラスターで方向転換して再びワープに入ることになる ("Fury" [VGR])。
初期のワープエンジンは重水素核融合炉からエネルギーを得ていたが、その後は正・反物質対消滅反応によって得るようになった。正・反重水素ガスを上手に混ぜ合わせると、エネルギービーム(プラズマ)が得られる。このビームは非常に高いエネルギー密度を達成し、エンジンの出す速度は飛躍的に向上した。しかし Warp5を越えることがどうしても出来なかったという。
この困難を解決したのが、ダイリチウム結晶 (dilithium crystals)である。ダイリチウム結晶を高周波電磁場の中に置くと反物質は結晶の中を素通り出来るのである。正・反物質対消滅反応は結晶の表面だけで起こるので、特定の方向にエネルギービームを集中させることが出来るようになった。この奇妙な性質は別の研究分野で偶然発見されたのだが、それがワープエンジンに応用されるに至った。この革命的技術改革により、ついにWarp5の壁はクリアーされたのである。USS Enterprise (NCC-1701)は、この技術が用いられた初期の船であった。なお、この反応炉は一般にワープコア (Warp Core)と呼ばれている。ENT以前では、動力源に核融合ではなく反物質を使っていたものの、ダイリチウムは使用していなかったようである。
反物質から膨大な得られるエネルギーが得られるとして、それがどうしてワープにつながるのか、詳細はわからない。ただ、このエネルギーのかたまりが「ワープコイル」というものをくぐりぬける時に亜空間フィールドが発生するらしい。電磁石に電流を流すと周囲に磁場が発生するのに似たイメージである。ワープエンジンのメインの部品は、このワープコイルである。ひしゃげた馬蹄のような形の部品が向かい合ってリング状をなし、これがたくさん並んでいる。エネルギー(プラズマ)を前方から後方に向けてワープコイルに流し込み、流れを正確に断続させることによってワープフィールドの衝撃波が生まれ、前方に船が進む。速度はプラズマのコイルへの投入量で調節される。船は十分なエネルギー状態に入ると、瞬時(プランク時間(1.3x10^-43 sec)以内 に)に光速を超えて発進する。
【徐々に加速して光速の壁を破るのでないところがミソである。量子力学における量子飛躍(quantum leap)のような現象で、アインシュタインの相対性理論による困難を回避している。】
The Rick Sternbach/Mike Okuda Tech Manualに拠れば、ワープ係数は整数でなくとも端数があっても良いとされている。もちろん Warp10を超えなければ。ただ、端数があるとエネルギー効率が極端に落ちるので、例えばWarp3.8は Warp4よりも多くのエネルギーを必要とするのである。これはワープフィールドが多層構造になっている事と関連がある。(補足解説を参照)
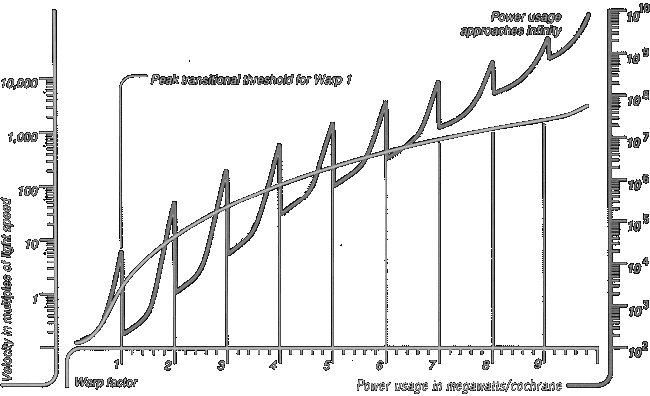
ワープフィールドは重力場と相性が悪く、互いに抑制する性質を持つ。そのため、強力な重力波バーストを受けると、しばらくの間ワープ航行不能に陥ることがある ("Once More unto the Breach [DS9]")。
TNGのEnterprise、NCC-1701Dは円板部と機関部側と分離できるように設計されている。円盤部はワープエンジンを持っていないが、少しの間ならば通常エンジンに付属する亜空間フィールド発生装置により場の崩壊を遅らせることが可能。短時間ならばワープ速度を維持できるのである。
光子魚雷がワープ出来るのもそれぞれが小さい亜空間フィールド維持装置を持っているからに他ならない。【光子魚雷・量子魚雷・機雷の項を参照】
前述したように、ワープエンジンの動力は反物質で、これはクリンゴン帝国のバード・オブ・プレイでも同じである。ロミュランのウォーバードでは、FQSD(Forced Quantum Singularity Drive)という方式を用いている。これはミニブラックホールを船内に設置してエネルギー源とするものである。
補足解説
ワープに入った時、最初の速度は Warp1である。ワープエンジンが出す速力は、ワープコイルに流れ込むプラズマ量に依存しているのであるから、このまま注入プラズマ量を増やして行けばいくらでも速度を上げることが出来るであろうか。
Warp1から増速して、Warp1.8->1.9->1.99->1.999と限りなくワープ係数を2に近づける事が理論上は出来る。しかし通常空間と亜空間との摩擦が増大して、エンジン効率は限りなく落ちて行き、このままではWarp2を超えることは出来ないのである。科学者達は、亜空間フィールド(亜空間殻)を多層構造にすることによってこの困難を回避したのである。
ワープ係数は、実は亜空間の層の数を表している。つまり、Warp2であれば亜空間フィールドが2層あるという事である。船が Warp1に入ったら、エンジン出力を充分に上げて、ある点(上のグラフの "Power Thresholds")に到達したら新たな高次の亜空間フィールドを作るのである。こうすると外部から見ると、船は2層の亜空間殻に包まれていることになる。こうして船は第2次亜空間を利用できるようになる。このとき船の速度はWarp2である。Warp2になると、エンジン効率は劇的に改善される。
あたかもクルマのギアを切り替えるように、Warp2->3->4->....->9と次々にワープ速度を上げる事ができる。しかし亜空間は第1次から第9次までしか存在しない(もしくは到達できない)らしく、第10次亜空間を造る事がどうしても出来ない。従って、現在のところ Warp10は到達不能速度(無限速)となっている。グラフにある通り、速度を上げるとエネルギー効率が極端に悪くなっていくのがわかる。しかしエンジンが物理的に耐え得れば、理論上はいくらでも速度を上げることができる。
トランスワープは、この壁を破る方法として期待されている。現在のところまだ軌道に乗っていないようである。
補足解説 2 --- ワープ航行中の景色について ---
TNG以降ではワープ航行中、虹のように星が流れる。よく見ると、近い星ほど速く長く流れており、遠方の星々は静止しているように見える。本当にこのような美しい光景を見ることが出来るのだろうか? もしそうならば、その景色を見るためだけにでもワープ船に乗ってみる価値があるというものである。
しかし、あの景色は言うまでもなく演出であって、確たる根拠があっての事ではないだろうが、そう言い切ってしまっては身も蓋もないので、少し考察してみよう。
ワープ航行している場合と、亜光速で航行する場合では、宇宙船の内部から宇宙を見た風景は根本的に異なるものと思われる。例えば、今 0.999cの亜光速で航行してる場合と、ワープエンジンで Warp 1(光速)で航行している場合は異なるであろう。その際、客観的な速度にはほとんど違いはないものの、航行している空間が異なるからである。
ではまず、亜光速で航行する場合について検討してみよう。
宇宙船に飛び込んでくる光は、走行する列車の窓からみた雨と同じように、船の速度の分だけ前方から入射するように見える(光行差)。船の速度が光速に近づくと、斜め後ろから来ているはずの光まで、前方からの光のように見えるようになる。そして限りなく光速に近づけば、宇宙のあらゆる星々は、真後ろの恒星(たとえば太陽)以外は、見かけ上、船の進行方向の一点に集中してゆく。ドップラー効果により、前方からの光は青色から紫外線、そしてガンマ線へと変化し、一方真後ろからの光は赤色から赤外線、さらには低周波電波へと変化してゆく。このように、進行方向を中心とした同心円状の虹のように見えることが予想される(この現象はスターボウ(星虹)と呼ばれている)。これはこれで美しいかもしれないが、期待した景色とはずいぶん異なる。
では超光速ではどうなるのだろうか?
もし、通常エンジンで超光速が出せるとしたら、我々はどんな景色を見ることになるのだろうか。もしかすると、とんでもない空間に突入して、とんでもない景色を見ることになるのかもしれないから、これも捨て難いかもしれない。ただ問題は、無事に帰還できるかどうかである。
だが幸か不幸か、相対性理論によれば通常エンジンで超光速は出せないことになっている。光速を越えるためには、ワープする必要がある。ワープエンジンは、船を強制的に亜空間に沈めて船を移動させる。確かに外部から見れば超光速で移動しているけれども、船自体は静止もしくは低速航行しかしていない。
船に到達する光は、船を包むワープフィールドを貫通して入ってくることになる。たまたまその場に居合わせた光がフィールドに捕らえられ、無事貫通して船の周囲にある通常空間に飛び出した時には、光子自身は相変わらず光速で飛んでいるつもりでも、いきなり超光速のベルトコンベアに乗せられた格好となって、結果的にワープしているわけである。質量を持つ一般の素粒子がこのようにワープフィールドをうまく貫通できるかどうかは分からないが、エネルギーそのものとも言える光子ならば可能という事かもしれない(そうでなければ、ワープ航行中は観測できない事になってしまう)。
上述したように、ワープエンジンは強弱の振幅を作って波状に次々と新しいワープフィールドを作りだし、常に脱皮して古い殻を後方に置いて行くかたちになる。そして、次第にフィールド強度が低下して波紋が消えてなくなるまで、一定時間は残っているはずである。この無数の波面が、それぞれプリズムのように機能して線状の虹(にじみ)を形成する可能性はある。その際に何らかの理由で、視差が大きい近い星ほどより長い虹を作るのだろう。
速度が上がれば、より高エネルギーの他のレベルのワープフィールドでも同様の現象が同時に発生し、全体として虹も長くなると考えられる。あの景色のメカニズムはこんなところではないだろうか。
ただ、これだけだと線状の虹が“流れる”ことはなく、夜の道路写真のように星の光が固定した線状のままで動かないようにも思えるが、ワープフィールドの形状が周期的に微妙に変化すると仮定すれば、虹が断続して流れるように見えても不思議ではないだろう。
もし船を静的で極めて強度の亜空間フィールドで上手に包めば、深海に沈んだ探査船のように、周囲の通常空間との接触は希薄になるかもしれない ("Remember Me" [TNG], "Suspicions" [TNG], "All Good Things..." [TNG])。しかしワープ時のフィールドは動的で隙があり、歪んだ形にせよ情報やエネルギーは通過するようである。
ただ、通過するといってもかなりの歪みやにじみが出るため、観測や通信には相応の補正が必要であることは間違い無さそうである。ワープ航行中のフェイザー発射は原則的に無効とされているが、確かにエネルギーがこのように拡散しては破壊力は期待できず、よほど上手に使わない限り事実上無意味であろう (ST1)。

Back
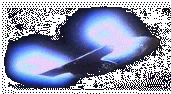
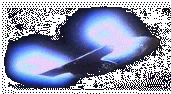
 Warp!
Warp! Warning! Damaged to warp core...
Warning! Damaged to warp core...