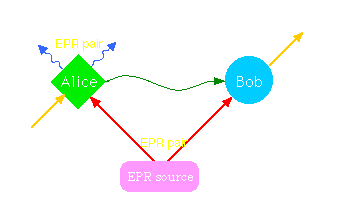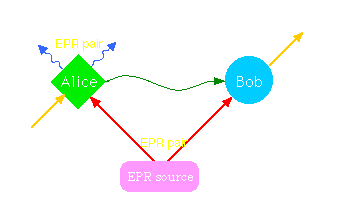量子テレポーテーション
テレポーテーションは、人や物を瞬間的に遠隔地に移動させる手法で、SFの世界では古くからあるアイデアである。テクノロジーによる方法もあれば超能力者の技として出てくることもあるが、いずれにしても想像の産物に過ぎなかった。スタートレックの転送技術も、たとえ遠い将来であっても到底実現するとは考えにくい。しかし1990年代に入ってから、非常に微かだが光明が見えてきた。スタートレックの転送技術のネックは量子レベルの不確かさであったが、この方法はそれを逆手に用いたものである。
■ EPRパラドックス ■
量子テレポーテーションを理解するには、その基礎となる“EPRパラドックス”をまず理解しておかねばならない。
“EPRパラドックス”(1935)のEPRとは "Einstein, Podolsky, Rosen"の3人の物理学者の頭文字である。アインシュタインは『神はサイコロを振らない』と言った。彼は、その有用性は十二分に認識してはいたものの、自然を確定的に記述できない量子力学というものに不快感を持って生涯抵抗し、量子力学を攻撃する数々の思考実験を考えては論敵のニールス・ボーア (量子力学の創始者の一人)を悩ませた。このEPR思考実験はその中でも最高のもので、アインシュタインら3人は元々量子力学を攻撃するつもりで考えたのだが、皮肉にも逆に量子力学の理解を深めるための至高のネタになってしまった。
量子力学によれば、素粒子の状態は観測するまで分からない。これは「本当は決まっているけれど観測するまで分からない」のではなく「素粒子は様々な可能性の重ね合わせの状態にあって、本当に決まっておらず、観測するまでどういう結果がでるか分からない」のである。さらにいえば、観測者にとって不確定というだけでなく、素粒子自身にすら分かっていない。量子の世界は一般常識が全く通用しない不思議な世界だ。
ある場所で2個の素粒子を発生させたとする。やり方はいろいろあるが、単一のイベントで2個の素粒子を発生させるところがミソであり、そうするとこの双子の素粒子は不思議な運命を共有することになるのである。量子力学では、これら2個の素粒子は途中で観測を受けるなど邪魔が入らない限り、いつまでも1つの方程式(波動関数)で表される。
この双子の素粒子は途中に障害物が無い限り永遠に飛び続ける。一方の素粒子を観測するために予定経路の途中に観測器を設置しておき、予定通り飛び込んだ時に属性の一つを測定するとしよう。もしこの素粒子に電子を用いるならばスピン、光子ならば偏光などが判明することになる。すると、2つで1つの関数なのだから、もう一方の属性もその時点で決定することになってしまう。この理屈には2つの素粒子の距離は無関係なので、もし仮に互いに一万光年も離れた時点で観測しようと、片方の観測結果が瞬時に一万光年彼方に“伝達”されてしまうことになる。しかし、いったい宇宙の彼方で起きた些細な出来事の影響が瞬時に伝わるなどということがあろうか?
アインシュタインらは、これでは光より速い速度 (実際は無限速)で情報伝達が起きてしまい、相対性理論に反すると考えた。ところが、ボーアの考え方は根本的に違っていて「2つの場所での出来事を分離して考えてはいけない。素粒子も実験に使う装置も、実験系をひとまとめにしてとらえるべきだ」と主張した。影響が瞬時に伝わったように見えたとしても、何も問題はないというわけである。こんなわけでアインシュタインとボーアの考え方は噛み合わなかったが、この思考実験は近年アスペ博士らによって検証され (EPR実験, 1982)、その後も何度も追試されてボーアの主張がほぼ正しいことが確認されている。
このように、最初の状態で深く関連付けられた2個の素粒子は“絡み合った素粒子 (entangled particles)”とか“EPRペア (EPS pair)”などと呼ばれ、外部から干渉を受けない限りテレパシーで繋がっているような不思議な関係が維持される。どんなに遠く離れようとも『2つで1つ』ということである。この双子の素粒子の間には見えない量子チャンネルがあり、観測されるとその関係は崩壊する。
とはいっても、我々一般人にとってこの現象は全く非常識で、簡単には受け入れることができない。しかしながら、量子力学の解釈のうち「多世界解釈」で考えると比較的わかりやすい(これは多世界解釈の強みでもある)。
理論上は無限遠まで影響を与え合うEPRペアではあるが、よくよく考えてみると、これだけでは意味のある情報を乗せて伝達することができないことが分かる。この系では情報を意図的にコントロールできないので仕方がないが、何かもう一捻りすれば情報伝達が可能になるのではないかと、誰しも期待する。
■ テレポーテーション ■
確かにEPR実験では意図的に情報を送ることは出来ないが、やはりというか、その後EPR実験を二段つなげることで可能になるだろうという論文が提出された (C.H.Bennet et.al., 1993)。下の図はその概念を模式化したものである。
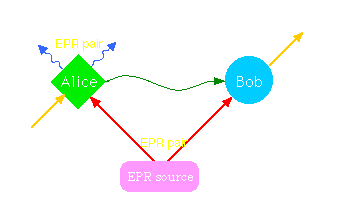
"EPR source"からは、絡み合った素粒子が対で2個づつ放出される。それぞれは互いに直交の性質 (電子ならばスピンの+/-、光子ならば垂直/水平偏光)を持つようにしておく。観測されるまではどちらがどの性質を持っているかは不明であるが、片方を観測した瞬間にもう片方の性質は自動的に決定する。観測されるまではどちらの結果でもありうる。(注:「直交」という用語は、「直角の交わり」という意味を代数的な意味に拡張した数学用語)
この研究は初めは光で行われていたので、これから先は素粒子を光子に限定して話を進める。さて、2個の光子はそれぞれ“アリス(Alice)”と“ボブ(Bob)”のところにやってくるように装置をセットしておく。アリスは送信側で、ボブは受信側である(“アリス”や“ボブ”の呼び名は、1993年のこの論文で用いられていたものだが、それ以後も好んで使われている)。
アリス側に光子Xが入射するのと同時に、送信したい情報を持つ光子Sが入射してぶつかるように上手に設定して、両者をここで再び絡み合わせる。アリスには観測装置があり、絡み合いの状況を逐一観測する。観測といっても偏光などを詳しく調べるわけではなく、光子の飛び方を見る程度である(これを「弱測定」という)。ペアになった後の2個の光子 (V, W)は「同時にまとめて」観測され、個々を追求することは敢えてしないが、その観測行為そのものがボブ側のYに影響を与えることになる。そして、もはやこの時点でVとWは、元来どちらがXでどちらがSだったのか判定不能となってしまっている (この不確かさを保存しておくことが非常に重要なのである)。
このような「中途半端な」アリス側での観測によって保持されたVとWの絡み合いは、4つのそれぞれ異なった量子論的な状態のどれかに帰着される。理論上それらは全て同じ確率で、それぞれの確率は1/4 (25%)づつとなる。「4つのうちのどれか」という、この僅かな情報だけが抜き取られ (2ビットの情報)、光子Sのほとんど残りの量子情報は、絡み合いを通じてSからX、XからYへと量子チャンネルを通して「瞬時に」伝えられる。アリス側での観測結果は通常通信 (D)によってボブ側に伝えられ、その内容に応じた処置をYに施せば、何と不思議なことに『YはSに変身』するのである。YとDに別れた情報が再構成され、Sが再登場したわけである。一方でオリジナルのSは絡み合って出所不明となり (V or W)、元来のアイデンティティー (情報)を失ってしまうので、複製を作ることはできない。
このようにして、結果的に光子Sは瞬間移動(テレポーテーション)することになる。Sが物理的に移動するわけではないが、素粒子レベルでは個々を区別できないので、量子論的属性が移転すれば完璧な複製となるのである。ただし、どうしても通常通信 (D)の併用が必要なため、残念ながら超光速通信に用いることはできない。
この図ではEPRは2段構造となっているが、理屈の上からは何段でも構わない。アリスの左側にアリス(2)・・・アリス(N)と、任意である。
1993年のこの論文は話題を呼び、世界各地で様々なアイデアで検証レースが始まった。そして遂に1997年にインスブルック大学 とローマ大学、1998年にはカリフォルニア工科大学で量子テレポーテーション実験に相次いで成功した。
インスブルック大学では、アリス側の絡み合わせの場にハーフミラーを用い、反射・通過後の2カ所の位置に検出器を置く実験を行った。上述の4つのパターンの内の1つでは、何の処置をしなくともYがSに変身することが理論計算上分かっていたので、その1/4のケースについてテレポーテーションを実証した。
翌年のカリフォルニア工科大学グループの実験では、さらに工夫されて効率もぐっと上がったという(残りの3/4のケースも含む)。VとWをフォト・ダイオードで検出し、それを一旦電気信号に変換してボブに送り、ボブ側ではそれを光に再変換してYに混ぜ合わせるという手法で成功した。また、アリス側に検出器をもう一つ置くことによって信頼性が上がったと言うことである。
2001年には、驚くべき事に1兆個もの分子を絡ませることにも成功したという (Polzik et.al.)。3cmほどの小さなガラスの容器に閉じこめたセシウム(ガス状)を2個1組用意し(それぞれに1兆個の分子が入っている)、それぞれを特定の磁場に置いた状態で、片方の容器にレーザービームを当てて量子情報を読みとり、それをもう片方の容器に照射したところ、0.5ミリ秒ほどの時間内ならばEPR状態を維持できたという。0.5ミリ秒というのはもとより充分にマクロ的な時間単位であるし、改良次第でもっともっと記録を伸ばすことは可能だろう。これはレーザーで原子に容易に情報を転送できることを示した画期的な成果だが、絡み合っているのは実は1兆個全部ではなく一部のみであった。
2004年には、光子ではなくて原子そのものを使ったテレポーテーションに成功したという報告が、インスブルック大学と米国立標準技術研究所の2施設から同時になされた。光子のような素粒子ではなく、前者はカルシウム原子、後者はベリリウム原子に上図のS/X/Yの役割を持たせた。交流電場を用いて極めて狭い空間に原子(イオン状態)を閉じ込め、周囲の環境から隔離された静かな状況下でそれらを物理的にくっつけたり引き離したりすることによりテレポーテーションに成功した。原子で成功したということは、将来のテレポーテーションに道を開くという意味で、極めて興味深い。ただ、この方法だと光の実験とは違って、実験チャンバー内部の狭い空間でないと実現しないため、SF的なテレポーテーションとしての派手さには欠ける。しかしこれは量子コンピューターの構造そのものでもあるため、量子コンピューター実現への重要なステップとはいえるだろう。
それ以降の時代に入ると、東大の古澤明らによって光子を用いた量子テレポーテーションは完成の域に達した。テレポーテーション効率が飛躍的に高まり、将来的にはほぼ100%に改善できそうである。さらに、AliceとBobという古典的な二者関係の拡張だけではなくて、絡み合った光子群を多者間の閉じたネットワークにすることに成功し、しかもそれらの間で重なりあった量子情報をも伝送できることが証明された。
このように量子テレポーテーションの基礎研究は次々と成果を挙げており、いずれ実用化されるかもしれない。ただ、今のところの主な応用は量子暗号通信や量子コンピューターである。
補足解説
研究が進んでいるからといっても、だからといって近い将来に物体のテレポーテーションが実現するとも思えないが、このペースならば何十年か先には単純な物ならテレポーテーションで物を送ることができるようになるかもしれない。しかし、だとしても人間を送ることは無理かもしれない。生命体だと、たとえ単細胞生物でも難しいことは明らかである。
しかしながら、単に無生物を転送するだけならば量子情報などは最初からさほど重要ではないわけであるから、生命を送ってこそ真価が発揮される類の技術かもしれない。上で解説したように、オリジナル粒子の量子情報は失われる。よって、もしオリジナルの物体を分解せずにスキャンできるなら、無生物の場合は結果としてコピーを作るだけということになるが、人間を転送した場合、オリジナルの人は送信元の転送チャンバーの中で転送オペレーターに看取られながら死ぬことになる。これは、一見魂が抜き取られたようにも見えるので、間違いなく各方面で大問題となるだろう。
量子テレポーテーションを用いた転送装置は、原理的にはスタートレックの転送装置と異なるものの、人間を転送するにはACBは量子情報を安全に保護するために必要だろうし、パターン・バッファもEPRペアを一時的に溜めるために必要である(安定性や検疫上の理由からも必要)。こう考えると、システム全体としては似かよったものになるかもしれない。

Back to "Transporters"